お店


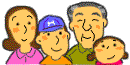
簿記の基本
簿記とは、会社で発生した取引を借方と貸方に分け、最終的に決算書を作成する記帳と計算の方法のことをいう・・・。簿記の基本書を見てみると、だいたいこのような表現で説明されています。 経理部で働いている人であれば、普段の帳簿作成の中で当たり前に使っている用語であっても、会計の知識や経験のない人にとっては、少し抵抗があるようです。
会社の経理の仕事には、現金の管理・仕入代金や経費などの支払、売上代金の請求回収・給料計算、支払いなどがありますが、これらの仕事と並行して、帳簿の作成・決算書の作成などの数字の整理作業も行わなければなりません。
会社の規模や業種にかかわらず、たくさんの数字を扱いますので、日々の取引を一般的に認められるルールに従って、一定の方法で数字を整理する必要があります。
簿記とは何か
|
簿記とは、一定のルールにもとづいて、会社で発生した取引(*「取引」参照) |
*簿記上の「取引」という言葉は、一般的に使われる意味とは異なります。
一般的にいう「売買の契約(取引)が成立した」は、簿記では帳簿に書き留めるべき取引には当てはまりません。
誰が記帳したとしても内容が変わらないような方法で、かつ分かりやすいものでなければなりません。簿記では記帳の仕方・手順が決められていて、すべての会社における会計の共通手段として使われています。
おおまかな帳簿記入の手順
|
1 仕訳をする(下書き作業) |
仕訳帳または伝票(振替伝票・入金伝票・出金伝票・売上伝票・仕入伝票) |
|
2 仕訳をしたらそのつど転記する (書き写す作業) |
仕訳帳または伝票→総勘定元帳・補助簿 |
|
3 総勘定元帳の各勘定の合計、残高を集め試算表を作成する |
総勘定元帳→試算表(合計・残高) |
|
4 決算期間ごとに決算作業を行い、決算書を作成する |
試算表(精算表)→決算書 |
コンピュータを使用して記帳作業をしている場合には、1の仕訳さえ正しく入力できれば、その後の転記・集計作業はすべて自動的に行われます。ただし、仕訳作業を間違えば、間違ったままのデータで作成されますので、何においても正しい仕訳をすることが大切になってきます。
仕訳とは
|
簿記では、すべての取引を借方と貸方に振り分ける作業を仕訳といいます。 |
簿記ではどんな取引も下記のように何をどこに記入するか、場所が決められています
例 商品を1000円で販売し(売上)、代金は現金で受け取った
| 商品が減る (交換) お金が増える お店   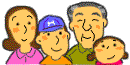 |
お店の主人の立場になって考えて見ましょう
この取引を簿記の約束事に基づいて仕訳すると
|
借方科目 |
借方金額 |
貸方科目 |
貸方金額 |
|
現 金 |
1,000 |
売 上 |
1,000 |
まず、簿記では上記のように半分ずつに分け、真ん中から左側の場所と、真ん中から右側の場所とを一言で表すのに便利な呼び名がつけられています。
| 真ん中から左側を「借方」と呼びます 真ん中から右側を「貸方」と呼びます |
仕訳の借方の金額と貸方の金額はどちらも1000で一致しています。
仕訳はてんびんが同じ重さのものでバランスをとるように、いつでも同じ金額でバランスが一致します。(バランスが一致しない仕訳はどこかが間違っているということです)
簿記では、文章で記録するとしたら (いつ)・何を・いくら・どうしたという事柄を整理する必要がありますが、上記の仕訳で、それらの事柄を表現しています。
そのほか得意先の名前や商品の種類や数量など簿記の仕訳で表現できない事柄は、仕訳を記入する仕訳帳や伝票の摘要欄というメモ書きをする場所に記録します。
貸方を見ると、商品の売上が1,000円あったことが分かり、借方を見ると、代金は現金で1,000円受け取ったということが分かります。
上記の仕訳の「現金」「売上」という言葉は、勘定科目といって、取引の内容を分かりやすくし、また、総称になるような呼び名を項目ごとに分類したもので、勘定科目(項目)ごとに勘定という集計場所を設けて記録します。現金を記帳・計算していく勘定を「現金勘定」、売上を記録、計算していく勘定は「売上勘定」といいます。
売上や仕入はそのまま勘定科目になっていますが、中には取引の内容がそのまま勘定科目にならない場合もあります。
従業員用のお茶を買ったときには「お茶」と仕訳するのではなくお茶に代表されるものの総称として「福利厚生費」という勘定を使います。
この勘定も仕訳と同じように、左側と右側の半分ずつに区切られていて、集計しやすいようになっています。
仕訳 借方の勘定科目が現金1000→現金勘定の借方に1000と記入
貸方の勘定科目が売上1000→売上勘定の貸方に1000と記入
| 仕訳をそれぞれの勘定科目の勘定に書き写すことを転記といいます。 |
現金勘定の借方は増加(プラス)を表現する場所で貸方は減少(マイナス)を表現する場所と決まっています。売上勘定の貸方は発生(プラス)で、借方は消滅(マイナス)を表現する場所と決まっています。
どんなものが何勘定になるのか、また勘定の性質によって借方・貸方のどちらがプラスの意味でどちらがマイナスの意味なのか、簿記の約束事としてあらかじめ決められています。
なお、会社によって使用する勘定や会計処理の方法が多少異なる場合があります
|
タンスのように、集計したい項目ごとに引き出し(勘定)が用意され、次々と出てくる取引を分類(仕訳)し、借方・貸方に区別して引き出しに入れていきます。(勘定に転記) 基本的には右側(貸方)にお金の出どころやお金の増える原因となるものを、左側(借方)にお金の運用状態(使い道)やお金の減る原因となるものを記録します。 最終的には財産の状態を貸借対照表という一覧表で、経営活動の成績を損益計算書という一覧表で報告することを目的としています。取引を表現する勘定科目は性質によって、資産・負債・資本・費用・収益の5つのグループのいずれかに分類され、資産・負債・資本の3つの組み合わせで財産の状態を表現し、費用・収益の組み合わせで経営活動の成績を表現します。 |
会社は元手である資金を増やすための活動を行い、利益はその後の活動資金として会社の財産に加えられます。
借方 貸借対照表 貸方 借方 損益計算書 貸方
|
資産 資金の運用状態 (資金がどんな状態に形を変えたか) |
負債 他人からの借入など |
儲けを増やして会社の資金を増やす |
費用 資金を増やす経営活動の中で消費・失われたお金 |
収益 資金をふやす経営活動の中で獲得したお金 資金の増加原因 |
|
|
資本 資本主からの出資・儲けの蓄積 返済しなくても良い資金 資本金 利益の蓄積 |
|||||
|
利益(儲け) 経営活動の成果 |
お金の使い道 お金の出どころ 収益−費用=利益(資金の増加)
資産のグループに当てはまる勘定科目
|
資産の勘定 プラスの財産(持っていればそれだけ会社の財産が潤うもののグループ) 金銭・金銭的な価値のあるもの・権利など 資産の勘定の借方はプラスを意味する場所→資産の勘定科目が増加したときは借方 資産の勘定の貸方はマイナスを意味する場所→資産の勘定科目が減少したときは貸方 借 方 貸 方
|
現金・当座預金・受取手形・売掛金・商品・前払金・未収金・仮払金・有価証券・前払費用・
建物・車両運搬具・土地など
負債のグループに当てはまる勘定科目
|
負債の勘定 マイナスの財産(会社の借金など債務の部分) 将来の支払い義務やサービスの提供義務など 負債の勘定の貸方はプラスを意味する場所→負債の勘定科目が増加したときは貸方 負債の勘定の借方はマイナスを意味する場所→負債の勘定科目が減少したときは借方 借 方 貸 方
|
支払手形・買掛金・借入金・前受金・未払金・預り金・前受収益など
資本のグループに当てはまる勘定科目
|
資本の勘定 正味の財産 資産の総額から負債の総額を差し引いた正味の財産(自己資本)のこと 出資金額や利益の留保 資本の勘定の貸方はプラスを意味する場所→資本の勘定科目が増加したときは貸方 資本の勘定の借方はマイナスを意味する場所→資本の勘定科目が減少したときは借方 借 方 貸 方
|
資本金・利益準備金など
収益のグループに当てはまる勘定科目
|
収益の勘定 資本の増加の原因になる収入 会社が営業活動などによって獲得した売上や営業活動以外で得た受取利息・受取手数料などが含まれる。 収益の勘定の貸方はプラスを意味する場所→収益の勘定科目が発生(増加)したときは貸方 収益の勘定の借方はマイナスを意味する場所→収益の勘定科目が消滅(減少)したときは借方 借 方 貸 方
|
売上・受取手数料・受取利息・受取家賃・雑収入など
費用のグループに当てはまる勘定科目
|
費用の勘定 資本の減少の原因になる支出 会社の営業活動のためにかかった経費など。 費用の勘定の借方はプラスを意味する場所→費用の勘定科目が発生(増加)したときは借方 費用の勘定の貸方はマイナスを意味する場所→費用の勘定科目が消滅(減少)したときは貸方 借 方 貸 方
|
仕入・給料手当・広告宣伝費・旅費交通費・通信費・接待交際費・消耗品費・福利厚生費・支払地代・支払家賃・保険料・租税公課・支払利息など
仕訳の考え方
仕訳は、家計簿のような現金の入出金のみに着目して記録するのではなく、物や権利・義務など、目に見えないものについても記録し、また会社の儲けが生み出されるまでのプロセスを原因別に整理し.会社のお金が増減する原因になるものすべてを盛り込みます。
仕訳例
|
商品を10万円で販売し、代金は現金で受け取った |
現金が10万円増えたので、現金勘定の借方に記入します
商品を売り上げたときは、売上という収益の勘定の貸方に記入します
|
借方科目 |
金 額 |
貸方科目 |
金 額 |
|
現 金 |
100,000 |
売 上 |
100,000 |
商品が減っているため商品という資産の勘定を減らす記帳方法もありますが、一般的には商品の売値の総額を売上勘定という収益の勘定で処理する方法が用いられます。
|
普通預金口座に現金を3万円預け入れた |
普通預金という資産が3万円増えたので、普通預金勘定の借方に記入します
現金が3万円減りましたので、現金勘定の貸方に記入します
|
借方科目 |
金 額 |
貸方科目 |
金 額 |
|
普 通 預 金 |
30,000 |
現 金 |
30,000 |
|
普通預金口座から5万円引き出して、当座預金に預け入れた |
|||
|
借方科目 |
金 額 |
貸方科目 |
金 額 |
|
当 座 預 金 |
50,000 |
普 通 預 金 |
50,000 |
|
普通預金に対する利息が100円入金されていた |
|||
|
借方科目 |
金 額 |
貸方科目 |
金 額 |
|
普 通 預 金 |
100 |
受 取 利 息 |
100 |
|
従業員のクリーニング代1万円を現金で支払った |
従業員のクリーニング代は費用の勘定である「福利厚生費」で処理します。
|
借方科目 |
金 額 |
貸方科目 |
金 額 |
|
福利厚生費 |
10,000 |
現 金 |
10,000 |
ここでは、簿記の基本中の基本をまとめましたので、これだけの知識でいきなりすべての仕訳ができるようになるわけではありません。簿記の考え方に慣れてきたら、基本書などで仕訳の勉強もしてみてください。